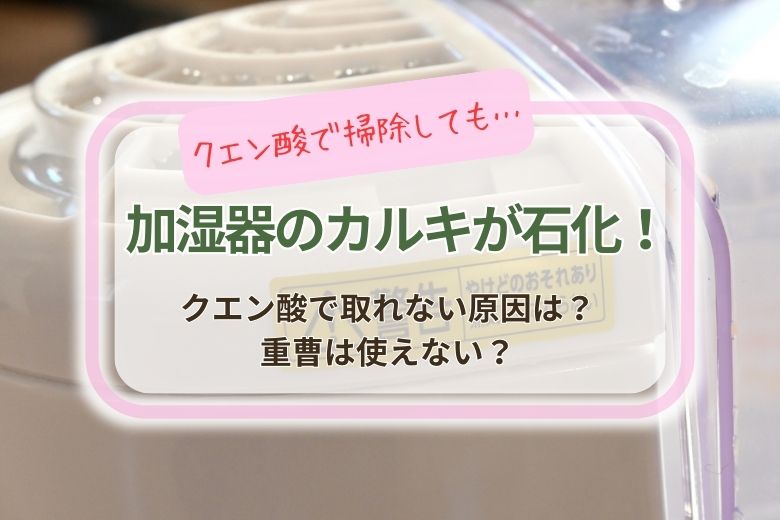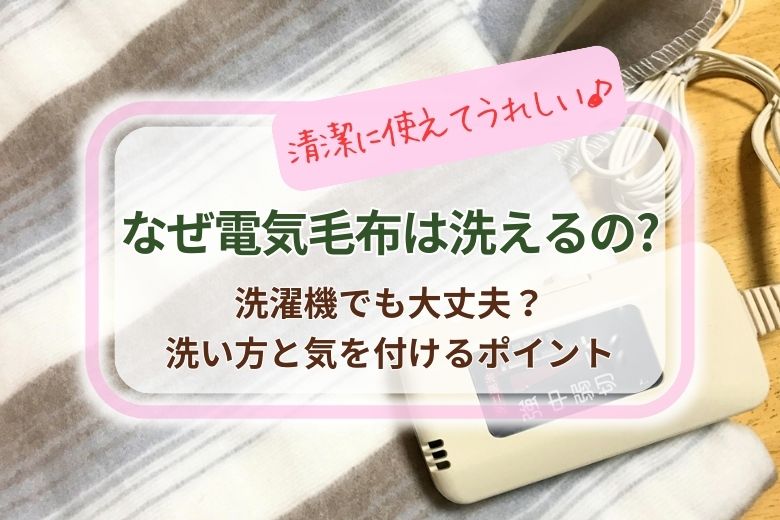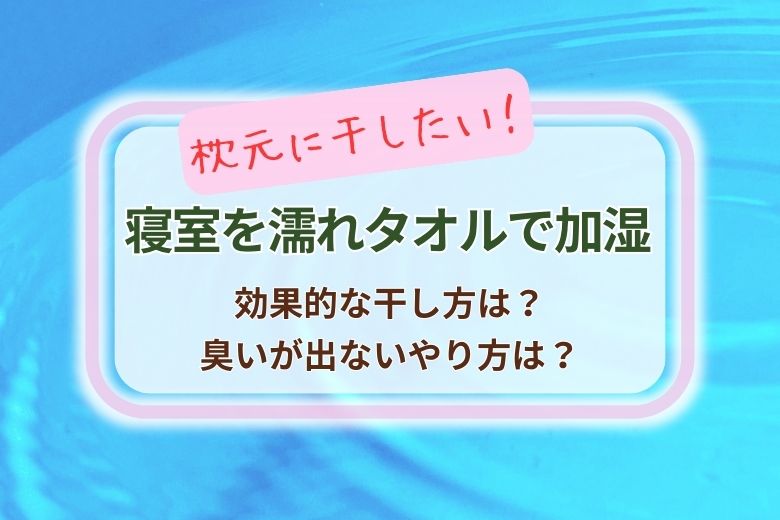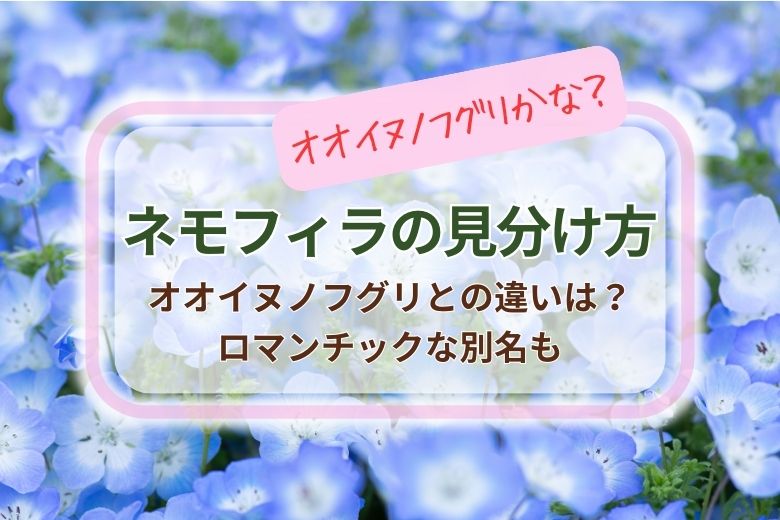耳元で「プウゥ~ン」…蚊が気になる季節になりましたね。刺されて痒くなるのも困るけど、なにより睡眠の妨げになるのが許せません。
最近は蚊取りも電気式のものやスプレーなどいろんなタイプが出ていますが、私は昔ながらの蚊取り線香が大好きなんですよ。

わぁ、蚊取り線香、子供の頃よくありました。あの煙の匂い、懐かしいですね。
私も使ってみようかな?でも、使い方がよくわからないな…
あのなんともいえない香りがノスタルジーを誘うんですよね~
使い方は、蚊取り線香に付いている缶が線香皿になるのでカンタンですよ。吊り下げタイプも便利だし、カワイイ豚の蚊遣なんかもありますけどね。
では今回は、蚊取り線香の使い方や注意点などをまとめることにしますね。
昔から日本の夏といえば蚊取り線香!ぜひ使ってみましょう~
蚊取り線香の缶はフタが線香皿?使い方は?
缶タイプの蚊取り線香は、線香皿が付属していますので特別に用意しなくても大丈夫です。
蚊取り線香の缶 セットの仕方
缶のフタの部分が線香を焚く皿になっていて、下の部分に蚊取り線香が入っています。フタをひっくり返す感じで缶の上に置くと、線香皿として使えます。

蚊取り線香は、2本ずつ組になっていますので、まずこれを外してあげます。折れそうでちょっと怖いんですが、中心の穴のある部分から少しずつずらすようにすると、うまく外れますよ。
蚊取り線香の先端にライターなどで火を付けます。煙を直接吸い込まないようにしてくださいね。
線香皿のカバーをはずし、線香をマットの上に置きます。線香が皿のフチに触れないように真ん中に置き、カバーをしてから使いましょう。
缶の線香皿には、火の付いた蚊取り線香を直接置くことができます。グラスウールという素材でできた不燃性のマットが敷いてあるからです。
このマットは使うたびに焦げたり、ヤニやススで汚れたりして黒くなりますが、そのまま何回も使うことができます。

次に使うときは、燃えたあとの灰を捨ててから新しい線香を置いてくださいね。
線香皿にタールのように付いたヤニは立ち消えの原因になるので、汚れたら中性洗剤で洗ってください。10巻使ったら洗うくらいの頻度をおすすめします。
蚊取り線香用のマットは取り替えできる?
グラスウールのマットは使い捨てではありませんが、真っ黒になってボロボロになってしまうとやはり耐熱性が落ちたり、線香の火が消えやすくなったりしてしまいます。
汚れが気になってきたら、消耗品として早めに取り替えたほうがいいでしょう。
火を使うものなので、アルミホイルなどでの代用もするべきではありません。必ず蚊取り線香用のグラスウールのマットを使ってください。
取り換え用のマットは市販されていますが、シーズンになると売り切れになる場合も多いので早めに用意しておくといいですよ。
線香皿なしの少量タイプから試したいとき

線香皿が付いた缶タイプの製品は、蚊取り線香が20~40巻くらい入っています。
はじめは10巻くらいの少量から試してみたいと思うかもしれませんね。でも少量の製品は付属しているのが線香立てだけなんです。
その場合は、陶器の皿などの上に、線香立てを置いて使います。使わなくなった食器などを用意してください。
火の付いた部分がむき出しになるので、蓋付きの線香皿よりも置き場所に気を使うようにしましょう。
蚊取り線香の置き場所 室内ではどこに?
蚊取り線香を置く場所についてご説明しますね。
蚊取り線香は、火が付いている部分から有効成分出て、それを煙が広げていく仕組みです。効き目が届くのが目で見て分かる感じですね。
ですから、風上に置いて部屋の隅々まで煙が行き渡るようにします。室内で使う場合は、窓際などに置くといいでしょう。
煙は下から立ち上るので、低いところに置くと効率がいいです。蚊が入ってきやすい玄関に置くのもおすすめですよ。
必ず換気をしましょう!
蚊取り線香を室内で焚くときは、窓を開けて風通しを良くし、煙がこもってしまわないようにしましょう。
蚊取り線香は、子どもやペットがいる部屋でも使うことができますが、換気には十分に気を配ってくださいね。
屋外でも蚊取り線香 吊り下げタイプも便利
蚊取り線香は屋外で使うこともできます。
犬小屋が外にある場合、ペット用の蚊取り線香を炊いてあげるといいですね。
アウトドアで広い範囲に使いたいときは、場所を分けて何個か設置すると風向きが変わっても効き目が安定します。
屋外での作業中に使う場合、歩き回りたいときは、吊り下げタイプの線香皿を使って腰からぶら下げるといいでしょう。
吊り下げタイプの線香皿は、中で線香が固定されるようになっていて、ズレて火が消えたり肌に触れてやけどをしたりしないように設計されています。
フックでいろいろな場所に引っ掛けて使うことができるのでとても便利です。
必要な時間が短いときはミニサイズがいいですね。かわいいデザインの商品もいろいろでています。
蚊取り線香はどうして豚? 使い方は?

蚊取り線香といえばイメージしてしまう豚の形をした線香入れは「蚊遣り豚(かやりぶた)」といいます。
有名なのは三重県の萬古焼や愛知県の常滑焼ですが、常滑市の養豚業者が使い始めたものが
お土産として広まったという説があります。
効率の良い形状を追求していくうちになんだか豚の形に見えてきたので豚の焼き物にしちゃったというんですね。
また、実は江戸時代からあったんだよ!という説も見つけました。東京の武家屋敷で使われていたものが発見されたんだそうです。
もっとも、そのころは今のような蚊取り線香はないので、杉などの木の葉っぱやおがくずなどを燻して虫よけに使っていたんだとか。
蚊遣り豚の使い方

蚊遣り豚は、中の空洞に蚊取り線香を吊るして使います。
後ろは蚊取り線香を入れるために大きく空いていて、前は少しずつ煙が出てくるようにすぼまっています。この形が豚に似ているんですね。
蚊遣り豚は持ち運びができるように取っ手が付いていますが、火を付けてから持ち歩くものではありません。適切な場所に設置してから火を付け、できるだけ動かさないようにしましょう。
蚊取り線香の香りって、季節感や懐かしさが感じられていいものですよね。 殺虫剤としては自然な感じがするところも好きだし、人や犬猫などのペットへの害もないので、我が家では今でも愛用しています。 ただ、気になるのがヤニです。 …
まとめ
今回は、蚊取り線香の使い方についてまとめました。
缶の商品を買えば、フタが線香皿になるのですぐに使うことができますね。
蚊取り線香はかんたんに使えるアイテムですが、火を使い、殺虫成分を含むものですので、換気や置き場所に気を付けて正しく使うようにしましょう。
蚊取り線香の香りをかぐと、子供の頃住んでいた実家の縁側を思い出します。
猛暑のため蚊が少ないといわれる最近の夏ですが、過ごしやすい夜はエアコンを消して窓を開け、蚊遣り豚とうちわを楽しむのもいいですね。